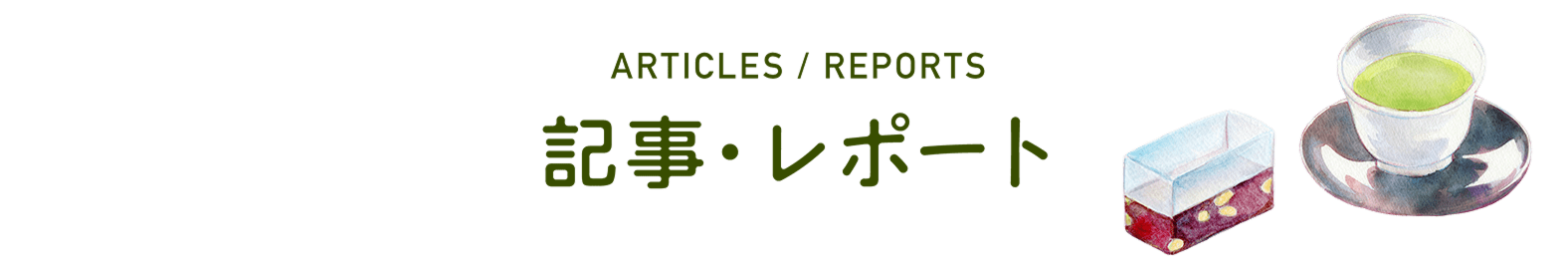特別インタビュー⑥公益社団法人 京都府茶業会議所 会頭 堀井長太郎さん
世界的な抹茶ブームの中、宇治茶ブランドを守る秘策
世界で抹茶ブームが巻き起こり、今まで以上に注目を集めるようになった宇治茶。その生産・流通を両面から支えるのが京都府茶業会議所です。その会頭を務められている茶商である堀井長太郎(ほりいちょうたろう)さんに、宇治茶が他の日本茶と一線を画すようになった経緯と理由、そして宇治茶が今後向かうべき姿について伺いました。
宇治茶が特別なお茶である理由

- はじめに京都府茶業会議所の活動について教えてください。
宇治茶の生産者およそ700名からなる京都府茶生産協議会と、その販売を担う約120の流通業者が加盟する京都府茶協同組合を会員とする公益社団法人です。
宇治茶の振興や普及、啓発のためにさまざまな事業を行っています。10月には大阪・関西万博で“覆い”を被せた伝統的な宇治茶の生産現場を披露し、宇治茶がどれほどの手間を掛けて栽培されるかを知ってもらおうと思っています。
他にも学術研究や、生産者が品評会へ出品する際の資金面での援助などを担っています。
- 宇治茶と一口にいっても、抹茶や玉露、煎茶、かぶせ茶など種類が多く、摘み方や製法もさまざまですよね。宇治茶とは何でしょうか?
宇治という場所は水捌けがよく寒暖の差があり、日照時間の面からも茶作りにおいて最適な環境です。宇治茶は、その気候や風土を生かして育まれた“素直な味”のお茶だと思います。
“素直な味”を紐解くと、雑味を感じず、口の中でスーッと広がるような味わいのことです。この代々受け継いだ茶園と茶作りの基本によって生まれる”素直な味”を守りながらも、各生産者が一歩上に出ようと”覆い”の掛け方や肥料の選び方などを追求することで、個性が生まれてきました。
- さまざまな工夫を施し、切磋琢磨することで磨き上げられてきた宇治茶。最近、紅茶が売られているのも見ました。こういった新しいお茶に対する考え方も教えてください。
今は抹茶をはじめ宇治茶がブームともなっていますが、茶業界全体でみると特に玉露といったリーフ茶(急須で淹れる茶葉の状態のお茶)が低迷したこともありました。
宇治で栽培される紅茶は、お茶の魅力を知ってもらうための新しい取り組みとして、煎茶以外に新芽を飲んでもらえないかと生産者が個性を発揮した結果なのだと思います。
各生産者のチャレンジ精神の高さと、それを認める業界の懐の深さを感じました。
- 今は宇治茶を求める海外からのお客様が非常に多いとお聞きしています。特に抹茶が手に入りづらくなっているそうですが、茶業会議所はどのような対策を考えられておられますか?
コロナ禍をはじめ大変なときに支えてもらった方々が飲めない、あるいは今までの2倍3倍のお金を出さないと買えない、という状況は心苦しく思っています。
販売業者に「価格を下げてください」とお願いできないのが、難しいところです。宇治茶は生産と流通の両輪がうまく回り、発展してきたという歴史があります。
宇治茶ブランドを築いた立役者

手摘みされる宇治茶会館の裏手の茶園(7月撮影)
- 宇治茶の生産と販売について詳しく教えてください。
宇治茶は生産者が価格を決めるのではなく、茶商が価格を決めてきました。普通であれば茶商は1円でも安く買いたいと思うでしょうが、宇治では安ければよいということはなく、良いものは高い値で買っていたのです。宇治の茶商は品質を見極める力と販売力がありますから。
一方、質が低い茶葉に対しては指摘やアドバイスがされました。昔は茶園を持っていた茶商が多く、知識が豊富だったという背景もあります。
生産者だけでなく、販売サイドも宇治茶のブランドを作り上げていたということですね。
- 最近、若者を中心に自分でお茶を淹れて飲む人が少なくなっている傾向について、ご意見をお聞かせください。また、お茶になじみがない人でも自分で淹れたお茶を楽しむ方法があれば教えてください。
煎茶をはじめリーフ茶は、種類によってお湯の温度が異なり、淹れ方が難しいと思われてしまいます。そしてゴミが出るというのも面倒くさいと感じてしまうのではないでしょうか。ペットボトルのお茶で十分と思っておられる層に、いかにして急須で淹れるお茶の魅力を伝えられるかも課題でしょうね。
ただ緑茶は健康に良く、その良さに外国の方が気付き始めています。令和7年は宇治茶の需要も値段も急上昇し、宇治茶元年だと私は思っています。若い人に宇治茶の良さを気付いて欲しくもありますが、生産量が足りるかも気がかりです。
宇治茶の未来はいかに
- 茶業会議所が今後目指される方向性や、ご自身の目標があれば教えてください。
私は宇治茶のブランド向上を図るため、2018年にパリに行きましたが、その時は抹茶をはじめ宇治茶の認知度は低く、抹茶を飲める店は数店舗だけで探さないと飲めない状況でした。今は海外で抹茶を飲める店が増え、“世界の抹茶”といわれるようになってきています。
私が懸念しているのは抹茶が注目される今、生産者が丁寧に作った良いものと、そうではないものの区別がつかなくなることです。たとえば一番茶と二番茶、石臼で粉砕したかどうかなど、明確に分かるようにする工夫が必要です。
また、緑茶は海外でも作り始められましたが、宇治茶と同じクオリティに達するにはしばらく時間がかかりそうです。そういったものとの区別も大事になってきます。
お茶は淹れてみないと味がわからないことから、信用取引が行われてきました。宇治茶は生産者と茶商でその信用を築いてきたという伝統があり、それが宇治茶のブランド力につながっています。
宇治茶と他の産地を比べた際に、生産技術やノウハウはいずれ追いつかれてしまうかもしれませんが、他の産地が追いつけないものとして気候風土があります。生産者はその最適な気候風土の中で「性(しょう)の良いお茶」(=品質の良いお茶)を育み、さらに茶商はそれを丁寧に目利きしていく、ことが必要だと思っています。
インタビュアーコメント
農作物というと生産者に注目することが多いですが、宇治茶ブランドの向上には茶商も大きな役割を担ってきたということに驚かされた取材でした。私たち消費者は宇治茶を買い求める際、目利きする茶商にそれぞれの茶園やお茶の特徴を尋ねることで、新しいお茶の世界が開けるのではないでしょうか。