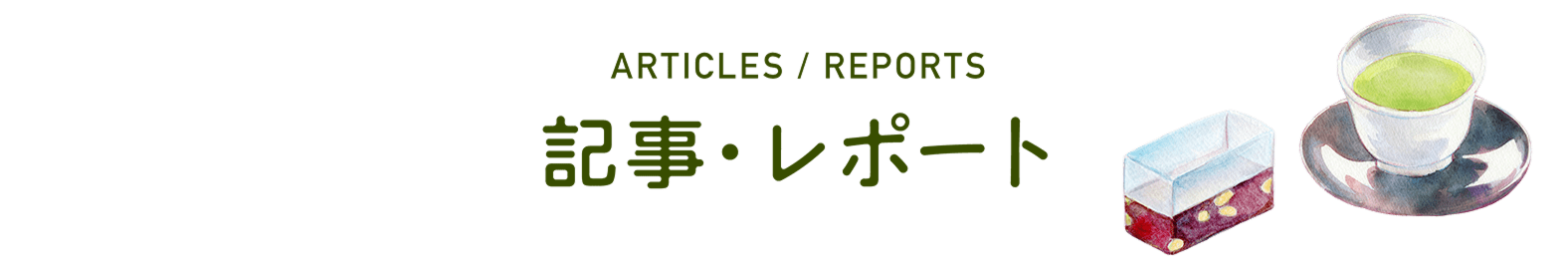特別インタビュー④煎茶道方円流 水口小園家元嗣
いつものお茶を特別なお茶に変える。“煎茶道”という魔法
「ありふれた、特別でないという意味の“日常茶飯事”という言葉の“お茶”は煎茶を指しますが…煎茶道となると、ふだんのお茶が一段ランクアップし『非日常のお茶』に変わります」。お話してくださったのは、煎茶道方円流の水口小園(みなくちしょうえん)家元嗣です。
今回は煎茶道の基礎知識や作法や手前、暮らしの中で『非日常のお茶』を作り出す秘訣について伺いました。
昔は茶会で絵を描いていた!?煎茶道のイロハ
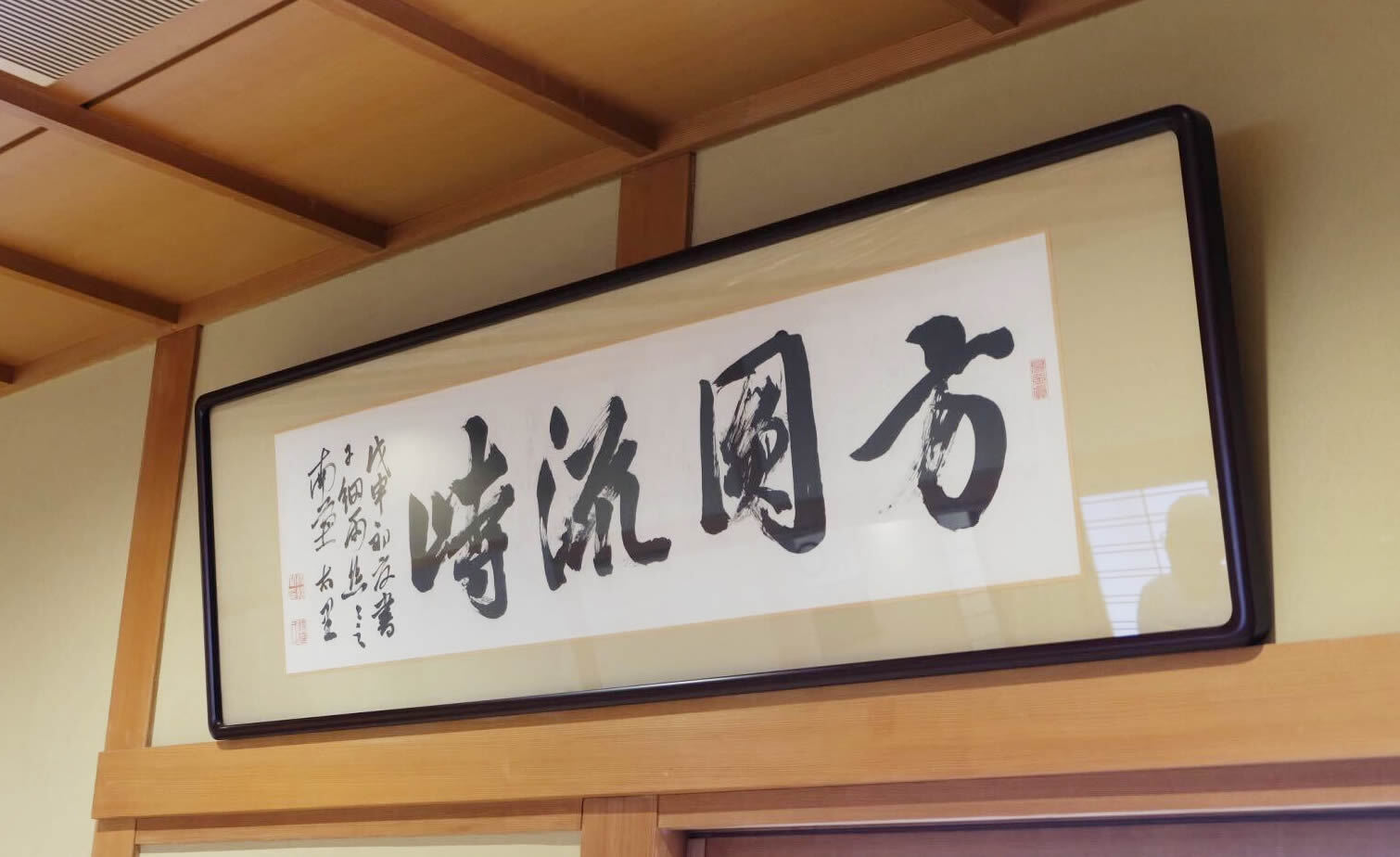
- はじめに煎茶道とは何でしょう?
煎茶道では、質・量とも平等に分けることを意識しながら、手前の者(客人にお茶を淹れる者)が一つの急須から茶碗にお茶を注ぎ分け、全員でいただきます。
近世に入ってから文人が自由な精神や風流を重んじ、会話を楽しみ、詩を詠み、歌を吟じ、絵を描きながら、心からお茶を愉しんでいました。文化サロンのような場であったのかもしれません。そのような雰囲気の中で“煎茶道”はひとつの“型”や様式として確立されて行きました。
方円流は煎茶道の流派の一つで、家元が医者の家系ということから、茶碗を清める際には、茶巾の面を一碗拭くごとに変えながら使用するといったように「清潔」をモットーにしてきました。
人によって味が変わる!煎茶道の面白さ

- 水口先生は今までどのような想いで活動されてきましたか?
何も知らないうちに活動を始め、その中でだんだんと見えてきたのかもしれません。年を重ねると多くの出来事に出会います。幸せな出来事も不幸な出来事も…。
茶会での経験ですが以前茶席で泣いてしまわれた男性がおられました。理由をたずねると、「亡くなった妻の淹れてくれたお茶を思い出して…」とおっしゃっていました。
きらびやかで高価な茶器を使うことの多い茶会であってもそれに頼ることなく、心を込めてお茶を淹れることで単に見た目重視の空間ではなく、心に届くお茶をふるまうことを念頭において活動しています。
- 先生のお茶をいただくとき、先生の優しさを受け取ったような温かい気持ちになりました。このような煎茶道の魅力は何だと思われますか?
やはり「味」だと思います。科学的に言うと、一煎目はアミノ酸がたっぷりと含まれるため甘み、二煎目は苦みと味の違いを楽しめます。そして同じ茶葉、同じ茶道具、同じ水を使って淹れても、淹れる人によって全く味が異なることが面白いと思います。ご年配の方が淹れてくださると、経験からか美味しいです。そして、席の中にいる人々の互譲の心を感じることができるのが、魅力だと思います。
人の思いやりが交わう煎茶道

- 初心者が難しいと感じる部分はありますか?
一つの急須から平等に茶碗へ分けるところでしょうか。多く入れすぎて最後の人の分がなくなってしまったり、逆に遠慮して少なく注ぐと余ってしまったり…
上手く注ぎ分けようと思うと緊張してしまいそうです…。
- 一方で、その緊張が和らぐ温かな空気感も印象的でした。
あってはならないことですが、参加者全員に茶碗を配るはずが、人数が多いと一人飛ばされてしまうこともあるでしょう。飛ばされた人は「私の分を忘れていますよ」とは言いにくいので、横の人が代わりに言ってあげる。そういうところで思いやりが生まれます。
お茶を通して人の優しさに触れるわけですね。
- その機会に出合える茶会はどのように参加できますか?
定期的に茶会を開いている神社仏閣、市区町村のイベントがあるので、ホームページをご覧になると良いかもしれません。(観光客向けのイベントなら、初心者でも参加しやすいです。)
家でも作り出せる『非日常空間』

- 日常の中で初心者がお茶に触れるには、どうしたらよいでしょうか?
自分の目の届かない、手の届かないところに、携帯電話を置いてくることからだと思います。急須に茶葉を入れ、お湯を注ぐことでお茶を淹れることはできますが、“非日常”の空間にはなりません。日常を非日常にするにはどうすればいいのかを考えると、よいかもしれません。
- 煎茶道ではどのようにお茶を淹れますか?
はじめに茶碗を清め、温めます。この所作には場と道具への、敬意と感謝が込められています。炭で沸かしたお湯を使い、お茶を淹れるのですが、茶葉の種類によって最適な温度や時間があります。
「美味しいお茶でおもてなしをしたい」という気持ちを持ちながら、一つひとつの意味を理解することが大切ですよね。煎茶道は道具が多いため、難しく思われることもありますが、理解できれば、自然と動けるようになります。
所作が美しかったのは、想いが込められていたからですね。
- 最後に目指される道について教えてください。
煎茶道は、今よく耳にする“タイパ”とは逆方向と言えるのではないでしょうか。急須に茶葉を入れ、お湯を注ぐ。そのあと、数分間お茶が滲み出てくるのを待つ必要があります。この「待つ」という行為がちょっと無駄だと思うのが現在の風潮です。
桜は蕾が膨らんで花が咲く…その過程を見ながら満開を待つことで、より美しく感じますよね。待つことから始まる会話、複数人で一緒にお茶を愉しむことで生まれる一体感、あるいは“孤”ではなく“個”としても満足できる…そんなことを目指しています。
煎茶道のこころに「相手を傷つけない」とありますが、現実は色々な事があり、そうはいきませんよね。せめて茶室の中は平等で、平和に愉しめる場であってほしいと願っています。

インタビュアーコメント
人を思いやり、人から思いやられ、お茶を通して人の温かみを感じる煎茶道。先生から「待つ」時間を愉しむと非日常が生まれる、と教えていただきましたが、煎茶は長く滲ませると味が濃くなってしまうので、茶葉によりますが最適な時間は1分程だそうです。そのわずかな“待つ”という時間を日常生活に取り入れられれば、忙しい毎日の景色が少しだけ変わるかもしれません。