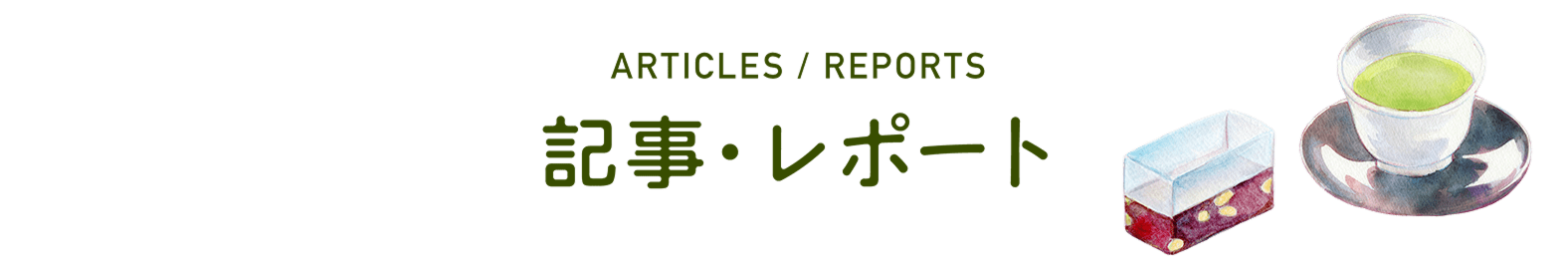特別インタビュー⑤日本茶インストラクター協会京都府支部 支部長 仲井敏雄さん
日本茶インストラクターに聞く、おもてなしの心を伝えるお茶の淹れ方
日本茶の最高峰とも言われる宇治茶。宇治茶を代表する玉露の名産地として名高い京田辺市で日本茶を販売する茶商として働く傍ら日本茶インストラクター協会京都府支部の支部長として日本茶の普及に携わる仲井敏雄(なかいとしお)さんに、美味しい日本茶の淹れ方やおすすめの種類、そして日本茶の中で宇治茶はどのような存在なのか―などについて伺いました。
日本茶のプロが語る「宇治茶の魅力」

- はじめに、日本茶インストラクター協会について教えてください
「日本茶を普及させたい、広めたい」という想いから2002年に発足した協会です。今では5,000人強の会員がおり、イベントを通して子どもから年配の方まで、幅広い層に日本茶の魅力を伝える活動をしています。
また日本茶検定も実施しており、日本茶の魅力を伝える人材の育成にも取り組んでいます。
- 日本茶と宇治茶はどういった関係性ですか
宇治茶は日本茶の原点だと思っています。歴史も長いですし、煎茶・玉露・碾茶…どの製法も宇治から生まれたといわれています。
“茶色には“茶”という漢字が入っていますが、もともとお茶は茶色だったのです。ところが宇治で独自製法が生まれ、緑茶ができました。
また宇治茶は見た目よりも味や香りを重視してきたという面もあります。飲んで本当に美味しくて良い香りがする日本茶…それが宇治茶です。
急須でお茶を淹れるという意味

- 日本茶のどういったところに魅力を感じていますか
日本茶はただ喉を潤す飲み物ではなく、文化を伴った飲み物だと思っています。
日本人は昔からお茶を通しておもてなしの心を示し、団らんのきっかけを生み出してきました。お客様がいらっしゃったときに、奥から給仕さんがお茶を持ってくるより亭主が自ら急須でお茶を淹れることで、より歓迎の気持ちが伝わりますよね。
確かに目の前で急須を使ってお茶を淹れていただくと「自分を大切にしてくださっているな」と心が温かくなりますね。
- 仲井さんはどのような想いを持って日本茶インストラクターのお仕事をされていますか
「急須でお茶を淹れる」という文化を広め、次の世代につないでいきたいです。普段お茶を淹れない方にも、美味しく淹れる方法を知っていただきたいと思っています。日本茶は、お湯の温度・お湯の量・お茶を抽出させる時間・茶葉の量、この4つの要素を自在に調整することで自分好みの味わいを出せます。
たとえば低い温度で淹れると、うま味成分のテアニンが多く抽出され、渋味成分であるカテキンはあまり抽出されません。自分好みの味わいが出せるような淹れ方を探してみるのも面白いと思います。
初心者でもできる!極上の一杯を淹れるには

- 美味しいお茶を淹れるにはお湯の温度が重要とのことですが、どのように調整すれば良いですか
沸騰したお湯は100℃ですよね。そこから茶碗に注ぐと10℃下がるといわれています。このお湯を別の茶碗に注ぐとまた10℃ほど下がります。煎茶を美味しく淹れる温度は70~80℃なので、茶碗に2~3回お湯を移し替えると、ちょうどよい温度となります。
あとは茶碗を持って、心地よい温度かどうかを確かめてみてください。触ってみて「熱い」と感じるなら、少し冷ましてから淹れる方がよいですね。
急須と茶碗さえあれば美味しいお茶を淹れられるということですね。
- 日本茶インストラクターとしての仕事と、茶商としての仕事に関連性はありますか
インストラクターの資格を取得するために、日本茶の歴史や効能など幅広い事柄を改めて勉強しました。
もともとお茶は薬として中国から日本に伝わってきました。それだけ体に良い成分がたくさん含まれた飲み物というわけです。たとえば眠気防止や覚醒作用は有名ですが、脂肪の吸収を抑える作用がありますし、抹茶には老化や生活習慣病を予防するビタミンEが多く入っています。お店にいらっしゃるお客様には、そういった効果面も伝えられるようになりました。
自分にぴったりの日本茶の選び方

- 日本茶に興味を持ったら、どんなことから始めたらよいでしょう
日本茶は嗜好品なので、自分が美味しいと思う日本茶を探すところから始められてはいかがでしょうか。日本茶を飲み慣れていらっしゃらない方だったら、個人的には煎茶から始めるのがおすすめです。
煎茶は自然を感じられるようなやさしい味わいで、後味が爽やかでさっぱりしています。一方、玉露は独特の余韻があるので、日本茶の魅力に気付かれた方は、ぜひ玉露も味わって、煎茶と玉露の違いも楽しんでほしいです。
- 一口に煎茶といってもさまざまな種類がありますが、どのような基準で選べばよいでしょう
茶葉には “普通蒸し”と “深蒸し”と、があります。 “普通蒸し”は軽やかな味わい、“深蒸し”は濃厚なテイスト、なので、好みの濃さから選んでみるのもおすすめです。ちなみに宇治茶は“普通蒸し”が多いです。
日本茶インストラクターが目指す今後の姿
- 今後、日本茶インストラクター協会が目指しておられる方向性や、ご自身の目標があれば教えてください
今は抹茶ブームですが「これを一過性で終わらせないためにはどうすればよいか」を考えています。そのためにはさまざまなイベントを通して日本茶を飲んでもらう機会をつくり、その良さに気付いてもらうことが必要だと思います。
たとえば、お茶を飲み比べて種類や産地を当てる“茶歌舞伎”(闘茶)もその一つです。飲んで当てなければならないとなると「日本茶の味や香りを覚えよう」という気持ちが生まれ、とても盛り上がります。お茶の良さに気付いてもらえるよう、これからも活動を続けていきます。
インタビュアーコメント
“おもてなし”の心を伝えられ、淹れ方によって味わいを自在に変えられる日本茶。思い通りの一杯を淹れられるまでには時間がかかるかもしれませんが、その試行錯誤こそが日本茶を楽しむ醍醐味だと感じました。
そして経験を重ねることで、相手の好みに合わせたお茶をお出しできるようになり、より心がこもった“おもてなし”へとつながっていくのではないでしょうか。