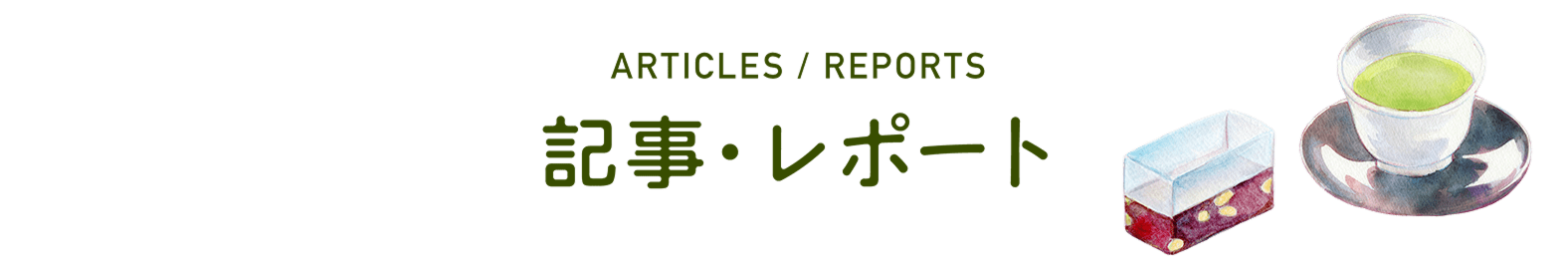特別インタビュー⑦京都府茶生産協議会 会長・𠮷田利一さん
どうして宇治茶は美味しいの?―日陰育ちの、特別なお茶が生まれた理由
日本茶と聞くと「宇治茶」をイメージする人も多いのでは…でも宇治茶って日本茶の3%にしか満たないそうです。
どうして宇治茶は生産量が少ないのに有名なのか―今回は、その秘密に迫ります。
京都府茶生産協議会の会長を務め、ご自身も宇治茶の生産者である𠮷田利一(よしだりいち)さんから、宇治茶が特別なお茶である理由について伺いました。
どうして宇治茶は美味しいの?

𠮷田さんが1年間大事に育て、摘み娘が1芽1芽丁寧に摘んだ茶葉
- 𠮷田さんが代表を務める京都府茶生産協議会とは、どのような団体ですか?
宇治茶の生産者によって作られた団体です。140年以上もの歴史があります。
私たちが頑張って育てたお茶は、消費者に届かないと飲んでもらえないですよね。届けるには卸売会社にお願いしたり、市場で売ったり、さまざまな方法があります。協議会は飲んでいただく方の元へ無事により良いお茶を届けられるよう生産者同士で情報交換をする場になっています。
- そもそも「宇治茶」とは、どのようなお茶なのでしょう?
京都府内または、その近隣の特定の地域で生産・加工された茶が宇治茶です。平安時代末期から鎌倉時代初期の僧・栄西禅師(えいさいぜんし)が宋から持ち帰ったお茶の実を、譲り受けた明恵上人(みょうえしょうにん)が京都の栂尾高山寺(とがのおこうさんじ)に植えたことが始まりとされています。
そして明恵上人は、宇治にもお茶の栽培を伝えていきました。
お茶を飲む習慣が広がった14世紀半ばはゲームも携帯電話もなかったので、お茶を飲んで産地を当てる遊び“闘茶”が流行っていました。その“闘茶”というのは当時は、高山寺のお茶を「本茶」と呼び、他の産地のお茶を「非茶」と呼んで、本茶がどれか飲んで当てるゲームでした。なんで高山寺のお茶を「本茶」と呼んだのか。それは、高山寺のお茶が美味しかったからです。

- どうして高山寺に植えられた、お茶は美味しかったのでしょう?
お茶の樹にはテアニンという、うま味の成分が作られていて、それがお茶の新芽に蓄えられた後に陽の光を浴びると、このテアニンが渋味の成分のカテキンに変わるんです。高山寺のお茶は、日当たりの悪い薄暗い土地で育てられていました。だから高山寺のお茶はうま味のある美味しいお茶だったんです。
そこで美味しいお茶を育てるには、直射日光を遮る必要があったわけですが、宇治でのお茶の栽培が進む中で、“覆い”が発明され、宇治のお茶も玉露や抹茶の原料の碾(てん)茶のようにうま味のある美味しいお茶になったわけです。また、宇治は京都の公家や武家文化とのつながりが強く、この覆いが許されたのは、かつては宇治だけでした。要するに宇治茶は、“覆い”と深い関係があるのです。
宇治茶と聞くと、日本茶の大部分を占めていると思われるかもしれませんが、実際は日本全体の生産量のわずか3%に過ぎません。生産量では他の地域にかなわないので、品質で勝負する必要があると思っています。
宇治茶は高くない!宇治茶の美味しい淹れ方

- 途方もない労力が掛けられた高品質の宇治茶―美味しく淹れる方法を教えていただけませんか?
茶葉はケチらずにたっぷり入れて、お湯は少なめにすると美味しく飲んでいただけます。茶葉が泳いでしまうようではお湯を入れすぎです
茶葉がもったいないと思われるかもしれませんが、そんなことはありません。上手に育てられ、加工されたお茶は四煎まで美味しく飲んでいただくことができます。
四煎まで飲めるのですか!
そうです。一煎目は低い温度で、二煎目からは徐々に温度を上げて淹れると美味しく飲めます。たとえば100gで3000円くらいの茶葉では、たっぷり一回に10g使うとしても、4人で分けて4煎飲むと考えれば…そんなに高くないと分かっていただけるのではないでしょうか。(一煎当たり18.75円。1人当たり75円)
1杯100円以下で飲めるわけですか…お茶は高いというイメージが変わりました。

- どうしたら、四煎も飲める茶葉が育つのでしょう?
生産も加工も、とにかく丁寧に行っています。
よく茶畑というと、子どもが遊んでいるイメージがあるかもしれませんが、宇治では茶畑で遊んでいると怒られます。樹や葉に傷が付いてしまったらどうするのかと。道具や水やりのホースも茶樹に当たらないよう気を付け、ものすごく大切に取り扱っています。
その後、大切に育てた茶葉の味をいかに落とさずに加工するかという話になってくるのですが、ここも丁寧に。うちの茶畑では、宇治茶の伝統的な製法を守っていて、茶摘みと揉み込み(摘んだ茶葉の加工)は手作業で行っています。
背中を見せて繋いでいきたい―宇治茶の未来

𠮷田さんの後を継ぐ2人の息子
- 長い歴史の中で、守り継がれてきた宇治茶。次の世代に、どのように繋いでいきたいですか?
宇治茶は一度でも飲んでもらえたら美味しさが分かると思うので、まずは多くの人に宇治茶を飲んでもらう機会を作りたいと思っています。
あとは後継者についてです。「子は親の背中を見て育つ」といいますから、頑張ってお茶を作っている背中を見せることだと思います。そして後世が跡を継ぎたくなるような、高品質のお茶を作れるよう励むことに尽きますよね。
インタビュアーコメント
宇治茶に限らず、世の中には数えきれないほどの飲み物がありますが、日光を遮る”覆い”を被せ育てられる飲み物は珍しいのだそう。そんな特別な手間を掛けて、大切に育てられた宇治茶…生産者の想いや努力を感じながら味わえば、お茶を飲むという日常が、優しさに包まれているような特別な時間に変わりそうです。