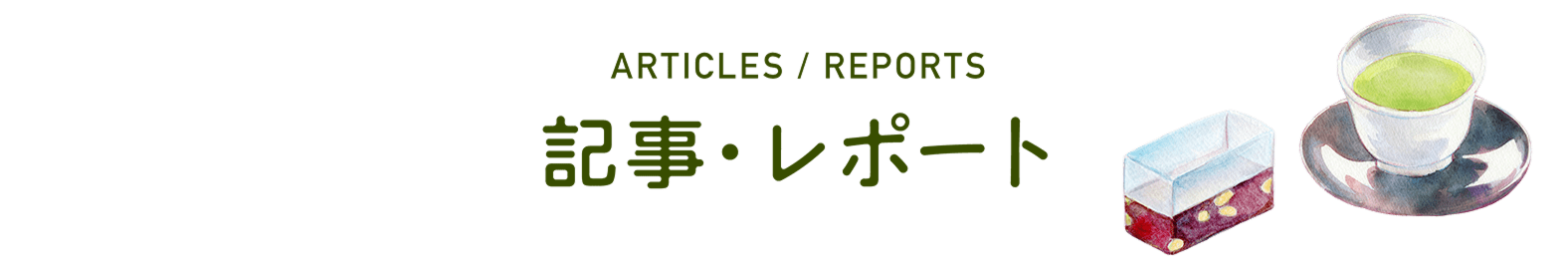特別インタビュー⑪高野竹工株式会社
手間と時間を重ねて伝える“竹の茶道具”という日本の文化
茶道の世界に欠かせない茶道具。その一つひとつには、茶道の精神が宿っています。今回は竹を素材に京都で60年以上、茶道具を作り続けてきた高野竹工株式会社(以下、高野竹工)さんに、竹で茶道具を作る想いや、茶道具はどのようにして生まれるのかについて伺いました。

竹を使った茶道具の魅力
はじめに高野竹工さんのショールーム『Shop & Gallery 竹生園(ちくぶえん)』で営業の井澤さんにお話を伺いました。

- 高野竹工さんでは、どのような茶道具を作っていらっしゃいますか?
抹茶を点てる茶筅(ちゃせん)と柄杓(ひしゃく)を除く、ほぼすべての茶道具を作っています。抹茶をすくう茶杓(ちゃしゃく)や茶碗、蓋置、花入(はないれ)など、茶道具にはさまざまな種類があります。
その中でも、当社では竹を使った茶道具を多く作っています。お茶は中国から伝わってきたもので同時に青磁や唐銅(からがね)等の道具も伝わり高価な道具が使われていましたが、日本で茶の湯が確立されていく過程で、日本の暮らしに身近な素材で茶道具が作られていくようになります。その代表的なものが竹と言えます。日本人にお茶が親しまれるようになり、茶道具も日本の暮らしに身近な竹で作られるようになったのだと思います。

- 竹は昔から日本人に親しまれてきたのですね。竹の魅力について教えてください。
強さとしなやかさ、どちらも持ち合わせていることです。茶筅をご覧いただくとわかりやすいのですが、ここまで細くしても折れないのは竹の強さとしなやかさのおかげです。
また、茶杓は、竹材の個々の個性をみどころとして、限られた形の中で、作り手の創造性や感性が如実に表れる道具でもあります。
茶道具を日常生活に取り入れるには
- 最近はペットボトルでお茶を飲む人も多く、茶道や茶道具に慣れ親しんでいない人も多いかと思います。
なにか日常生活に取り入れやすい茶道具はありますか?
当社のギャラリーには外国人の方も多くいらっしゃるのですが、茶道具一式を入れるために作られた茶箱を、茶道具ではなく趣味のコレクションを入れるために買い求められることもあります。いろいろな使い方ができるのだなと、こちらも勉強になります。
竹茶碗も、茶道をされない方でも使っていただきやすい茶道具です。軽く、落とした時に割れにくいのでアウトドアに持っていかれてはいかがでしょうか。リュックから竹茶碗が出てくるなんて、おしゃれですよね。


竹を伐るということ
- 竹を伐り出すという素材の調達から、竹の加工・表面装飾までを一貫して社内で行う高野竹工さんでは、竹林そのものの管理にも力を注ぎ、自然との調和も守り続けています。
高野竹工さんが管理する竹林に移動し、伐り子職人さんにお話を伺いました。

- 竹林を守るとは具体的にどのようなことをするのでしょうか?
竹は何もしなくても成長するというイメージを持たれやすいですが、人が手をかけなければ良い竹は育ちません。加えて竹林は荒れるのがとても早いです。まず、どの竹を残すかと考えその上で伐る竹を判断します。
- 竹林全体のバランスを考えながら、伐る竹を選ぶということですね。どのような竹を伐っていくのでしょう?
竹の寿命は15年ほどと言われ、2~3年の竹は人間でいう20~30歳くらいのイメージで、7年以上の竹は親竹にはならないとされています。したがって若い竹は残し、7年以上の竹を伐ると、竹林としては良いバランスとなるわけです。
ところが2~3年の竹は美しく青みを帯び、傷が少ないことに加えしなやかなため、竹籠をはじめ青竹・白竹製品として多く利用されます。そのため一般的に伐り子は残しておくべき若い竹ばかりを伐り、竹林には古竹が残されることになります。
一方、茶道具の素材として求められる竹は異なります。4~10年の竹は表皮に風傷やシミが付いていることも多いですが、茶道具では“侘び寂び”という独特の感性が根付いているので景色として味わえるわけです。

茶道具を作るということ
- 伐り出された竹は乾燥させた後、本社工場へ送られ、竹の加工・表面装飾に携わる職人さんの手仕事により茶道具に生まれ変わります。職人さんたちに、茶道具を作る醍醐味や難しさについて伺いました。

- 竹が職人さんの手に渡った後、茶杓はどのように形づくられていくのですか?
竹を削って形を整えた後、一時間くらい水に浸け素材を曲がりやすい状態にしてから、ガスバーナーを使い手で曲げていきます。
茶杓をはじめ茶道具には“型”があり、その“型”を守っていくことが大切です。作り手の感性を出しつつも、使い手の趣向に合わせたモノを作るよう努めています。

- 伐り子から繋がれた素材が茶道具に形づくられた後、どのように完成させるのでしょう?
下地を固めた後、漆を薄く何度も重ね塗り、磨き上げます。
竹を扱う際に気を付けていることは、色が入りにくいことです。木材と比べて固いため、濃くならないことを頭に入れながら色を塗っていきます。

- 竹を素材にした茶道具を世に送り続ける高野竹工株式会社。長年にわたる茶道具作りで信頼を積み重ねた結果、竹以外の素材で茶道具を作ってくれないかと依頼を受けることもあるそうです。金閣寺の古材を使い、茶道具を作ったこともあるのだとか。
50年以上茶道具を作り続ける指物職人さんは、どのように仕事へ向き合ってきたのでしょうか?
指物とはホゾ(凸)とホゾ穴(凹)を組み合わせる伝統技法です。
茶入れは密閉し湿気や空気から茶葉を守るものですので、隙間なくピタッと締められる指物の技術が役立ちます。
指物に携わって50年以上が経ちますが、お寺関係の古材をお預かりして茶道具を作ることもありますが、古材のどの部分を使えば長年使い続けられるか先を見越して、組んでいます。
次世代へつなぐということ
- 日本人の身近にあった竹、そして長年に渡り使い継がれてきた古材を、茶道具へ変えてきた高野竹工さん。最後に、今回の取材の案内役を務めてくださった井澤さんに今後の展望を伺いました。

抹茶が世界的なブームになっている現状もありますし、昔から茶道の世界で継承されてきた部分は大切にしながらも、日常で気軽に抹茶を楽しむ為の新しいアイデアの道具があっても良いのではと思っています。
もう一つ目指しているのは竹林を大切に守ること、そしてその竹を余すことなく使うことです。コロナ禍を経て日常的に使うものが見直され、自然素材に関するニーズが高まってきていると思います。一方、科学の進歩により竹に代わる材料も生まれ、竹は年々使われなくなってきています。
竹林を守るのも大変ですが、竹を伐って茶道具の材料となるまでも労力がかかります。2~3か月ほど自然乾燥させた後、熱を加えて油分と水分を抜き天日に晒して艶を出し、カビなどが生えないように気を付けながら最低でも3,4年という時間をかけて乾燥させていきます。じっくり乾燥させることで、長年にわたって愛用したくなるような、丈夫で素材そのものの良さを感じられる茶道具となるわけです。手間と時間がかかる竹という素材ですが、茶道具を通してその良さを次の世代に伝えられれば良いなと思っています。
インタビュアーコメント
取材で印象に残ったのは、「茶道の世界では、竹林の中で年月を重ねて現われるシミやこすれた模様も味わいのある景色になる」というお話です。茶道具には、不完全さにこそ価値を見出すという“侘び寂び”の精神が宿っているのだと改めて感じました。
今では「SDGs」という言葉で語られる持続可能性も、竹林を守り、素材を生かし切る茶道具づくりの中にすでに根づいていました。そのような素材の故郷や未来への思いやりが、茶道具の味わいとなっているように感じました。
私たちがいきなり茶道を始めるのはハードルが高いかもしれません。けれど生活の中にひとつでも茶道具を取り入れられれば、日本人が昔から大切にしてきた考え方に触れることができそうです。