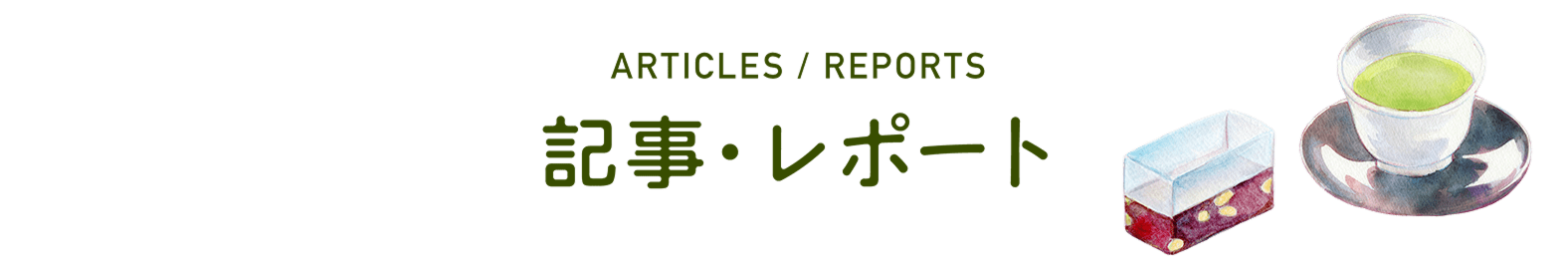学生プロジェクト
目次
茶室プロジェクト
2025年10月11日〜13日【学生・茶室プロジェクト】茶室完成・披露!
10月11日~13日の3日間、北野天満宮にて茶室プロジェクトのお披露目が行われました。プロジェクトの初めから関わらせていただき、伴走しながら取材を行って来た、楽しみにして当日を迎えました。
この3日間は、急須の普及のために実施したイベント「急須の日プロジェクト」を通して、学んだ、お茶の淹れ方も今回のお茶室を使って広めていくこととしていました。私たち京都府立大学の学生も、頑張って京都市立芸術大学の学生さんが制作した茶室で急須をPRしてきましたので、今回はその様子をレポートします!続きはこちら(PDF)
2025年8月22日【茶室プロジェクト】京都市立芸術大学に茶室の進捗状況の取材に伺いました!
8月22日(金)に、京都市立芸術大学へ茶室プロジェクトの進捗状況を取材しに伺いました!そこで、ゼミ生のみなさんによる茶室デザインの発表を伺うことができました。その様子をレポートいたします。続きはこちら(PDF)
2025年5月26日【茶室プロジェクト】お茶会に参加!!
茶室プロジェクトの第2回目として、茶室の専門家である京都建築専門学校副校長の桐浴邦夫さんと、茶室プロジェクトの主力メンバーとなる京都市立芸術大学の方々が、有斐斎弘道館で開催されたお茶会に参加されました。茶室について専門家の方からお話を伺うことができる貴重な機会となりました。その様子をレポートいたします。続きはこちら(PDF)
2025年4月28日 きょうとまるごとお茶の博覧会「茶室プロジェクト」がいよいよ始まりました!!
きょうとまるごとお茶の博覧会のグランドフィナーレイベントとして、10月11日(土)~13 日(月・祝)に北野天満宮にて「北野大茶会」の開催を予定しています。北野大茶会開催に向けて、北野天満宮に新しい茶室を作ろうというプロジェクトが立ち上がりました!主力メンバーは京都市立芸術大学の3年生から修士 1 年生のみなさん。第1回目の顔合わせ&勉強会の様子をレポートいたします。続きはこちら(PDF)
急須の日プロジェクト
2025年9月4日【学生プロジェクト】急須の日に「急須でお茶を淹れる会」の開催!
今回は、9月4日の「急須の日」にちなんで、コミュニティカフェ新大宮にて、急須の魅力を発信するイベントを行いました。当日の運営等についてその様子をレポートします!続きはこちら(PDF)